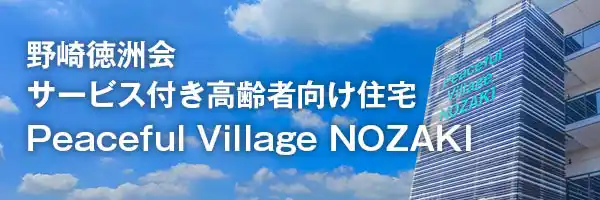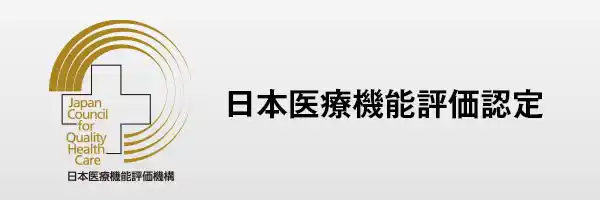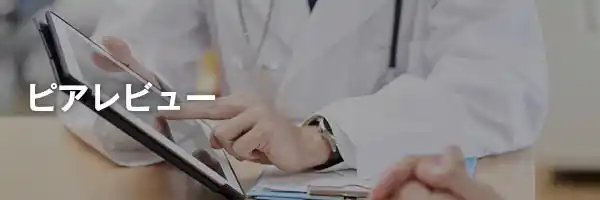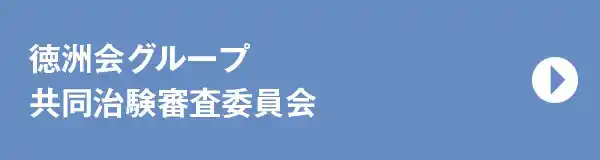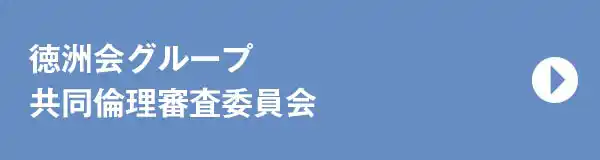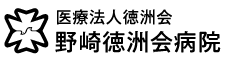新着情報
News
新着情報
News
ご利用について
Servise & Process

初診の流れ
初診の方へ、受付から診察、会計までの流れを紹介しています。

当院への交通について
電車、バス、お車など、当院へのアクセスを紹介しています。

発熱外来の予約
野崎徳洲会病院 抗原(コロナ)検査予約サイト
ご利用について
Examination & Visitation

初診の流れ
初診の方へ、受付から診察、会計までの流れを紹介しています。

当院への交通について
電車、バス、お車など、当院へのアクセスを紹介しています。

発熱外来の予約
野崎徳洲会病院 抗原(コロナ)検査予約サイト
診療科紹介
Departments
脳卒中、脳腫瘍、脊髄・脊椎疾患、けいれん・神経痛など
冠動脈の病気、心臓血管の病気、大動脈の病気など
虚血性心疾患、全身血管疾患、心不全、不整脈 など
外傷、各種ヘルニア、各種癌、下肢静脈瘤、大腸がん など
骨、軟骨、神経、筋肉、靭帯の疾病、外傷、運動外傷 など
肺癌、腫瘍性疾患、気腫性肺疾患、膿胸・肺化膿症、外傷性(血)気胸 など
患部にのみ放射線を照射できる治療機を用いた放射線治療
顔面外傷(骨折など)、智歯、顎関節疾患、顎変形症 、口腔癌・舌癌 など
小児一般疾患、感染症、気管支喘息、アトピー性皮膚炎 など
外来通院の患者様・入院患者様へのる血液透析治療、検査 など
病理組織診断・細胞診断・病理解剖、院外の医院様の病理診断対応
救急患者様の対応、当院救急車でのお迎え、緊急手術の対応など
風邪、発熱、頭痛、腹痛、糖尿病、高血圧、腎臓疾患、肝臓疾患 など
思春期から閉経後まで、婦人科診療・手術、月経相談 など
診療科紹介
Departments
脳卒中、脳腫瘍、脊髄・脊椎疾患、けいれん・神経痛など
冠動脈の病気、心臓血管の病気、大動脈の病気など
虚血性心疾患、全身血管疾患、心不全、不整脈 など
外傷、各種ヘルニア、各種癌、下肢静脈瘤、大腸がん など
骨、軟骨、神経、筋肉、靭帯の疾病、外傷、運動外傷 など
肺癌、腫瘍性疾患、気腫性肺疾患、膿胸・肺化膿症、外傷性(血)気胸 など
患部にのみ放射線を照射できる治療機を用いた放射線治療
顔面外傷(骨折など)、智歯、顎関節疾患、顎変形症 、口腔癌・舌癌 など
小児一般疾患、感染症、気管支喘息、アトピー性皮膚炎 など
外来通院の患者様・入院患者様へのる血液透析治療、検査 など
病理組織診断・細胞診断・病理解剖、院外の医院様からの病理診断依頼への対応
救急患者様の対応、当院救急車でのお迎え、緊急手術の対応など
風邪、発熱、頭痛、腹痛、糖尿病、高血圧、腎臓疾患、肝臓疾患 など
思春期から閉経後まで、婦人科診療・手術、月経相談 など